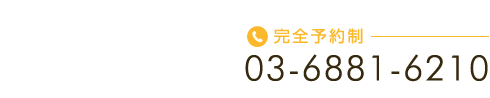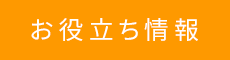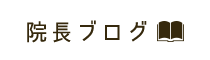冬になると「なんとなく体がだるい」「朝が起きられない」「食欲がない」と感じることはありませんか?これらは「冬バテ」の症状かもしれません。冬バテとは、寒さや日照不足、生活習慣の乱れが原因で起こる体調不良のこと。放っておくと体力が低下し、風邪やインフルエンザにかかりやすくなることもあります。今回の冬は、特にインフルエンザや風邪にかかってしまう方が多いように感じます。
この記事では、冬バテの原因と対策、寒い冬を元気に乗り越えるためのヒントをぜひ取り入れてください!
冬バテの原因とは?
冬バテは主に以下のような要因で引き起こされます。
- 寒暖差ストレス
冬は外の寒さと室内の暖かさの差が大きくなります。この温度差で自律神経が乱れ、疲労感やだるさを引き起こします。
- 日照不足によるホルモンバランスの乱れ
冬は日照時間が短くなるため、セロトニン(「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質)の分泌が低下します。これが気分の落ち込みや食欲不振につながります。
- 栄養不足
寒さによる代謝の上昇で体がエネルギーを必要とする一方、食欲の低下や偏った食生活で十分な栄養を摂取できない場合があります。
- 運動不足
寒い季節は外出を控えがちになり、体を動かす機会が減ります。これにより血流が悪くなり、疲労がたまりやすくなります。
冬バテ解消のための食事術
体の内側から冬バテを防ぐには、食事から摂る栄養がカギになります。以下のポイントを参考にしてみてください。
- ビタミンD
日照不足で不足しがちなビタミンDは、魚類(特にサバやサケ)や卵黄に豊富に含まれています。免疫力を高める効果もあるため、積極的に摂取しましょう。
- 体を温める食材を取り入れる
寒さによる冷えを防ぐため、しょうが、にんじん、かぼちゃなど体を温める効果のある食材を摂りましょう。これらはスープや煮込み料理にすると、体を効率よく温めることができます。
- タンパク質をしっかり摂る
疲労回復と代謝を促すために、肉、魚、卵、大豆製品を意識して摂取しましょう。筋肉量を維持することも、冷えの改善に役立ちます。
- 発酵食品で腸内環境を整える
ヨーグルトやキムチ、納豆などの発酵食品は、腸内環境を整え、免疫力を高める効果があります。腸内の状態が良くなると全身の疲労感が軽減します。
5.核酸を摂取する
核酸がなければ、タンパク質は作れません。筋肉や神経、免疫系を作るにも必要な栄養素となります。
冬バテ予防のライフスタイル
食事だけでなく、日常生活の工夫も冬バテ対策がとても大切です。
- 適度な運動を習慣化する
寒いからといって動かないのは逆効果。ウォーキングやストレッチなど軽めの運動を取り入れることで血行が促され、体が温まります。
- しっかり睡眠をとる
質の良い睡眠は自律神経を整えるために必要不可欠です。寝室の温度や湿度を適切に保ち、リラックスした状態で眠りましょう。
- 入浴でリラックス&血行促進
湯船に浸かることで体の芯から温まり、血流が改善します。炭酸ガス入りの入浴剤やエッセンシャルオイルを使うこともおすすめです。
- 日光を浴びる
できるだけ午前中に日光を浴びることで、セロトニンの分泌が促進されます。散歩やベランダでのひとときもおすすめです。
冬バテに効く簡単レシピのご紹介
最後に、体を温めるおすすめレシピをご紹介します。
しょうがと根菜たっぷりのスープ
材料(2人分)
- しょうが(みじん切り):1かけ
- にんじん:1本
- 大根:1/4本
- だし汁:500ml
- 味噌:大さじ2
作り方
- 野菜を食べやすい大きさに切ります。
- 鍋にだし汁を入れ、野菜を煮込みます。
- 野菜が柔らかくなったら、しょうがを加え、味噌を溶き入れます。
- 器に盛り付けて完成です!
しょうがの香りと味噌のコクで、体が芯から温まります。
冬バテ対策で寒い季節を快適に
冬バテは、日々のちょっとした工夫で予防できます。「食事」「運動」「睡眠」をバランスよく整えることがポイントです。この冬こそ冬バテを乗り越え、健康で快適な生活を送りましょう!
コラム執筆・監修者
合同会社 Rerise
つくし鍼灸整骨院
代表取締役 東 智博
・厚生労働大臣認定資格
柔道整復師 鍼灸師 専科教員
・経歴
墨田区内整骨院勤務14年
2019年7月 台東区北上野につくし鍼灸整骨院を開院